研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 主任 梅野博仁 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。
医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 主任 梅野博仁教授
所属部署について教えてください。
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、昭和3年に久留米市立病院を母体にして九州医学専門学校附属病院が誕生した際に開講した歴史と伝統ある耳鼻咽喉科学講座です。特に発声・嚥下・呼吸の機能を備えた喉頭に関する研究と、頭頸部癌に関する研究は60年以上にわたり歴代の主任教授が力を入れて取り組んでこられ、当講座における研究領域の主軸となっています。私は平成26年4月1日より第10代目主任教授に就任し、教室を主宰しています。最近では耳鼻咽喉科領域での再生医療にも研究分野を拡げています。大学病院は各専門分野のエキスパートが揃っていますので、他科とのチーム医療にも力を入れています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科の道を選ばれたきっかけを教えてください
父親が耳鼻咽頭科医院を開業しており、地域医療に専念する後姿を見て育ちました。私は次男でしたので、耳鼻咽喉科にこだわれず最初は消化器内科と脳神経外科に興味を持っていました。しかし、久留米大学の耳鼻咽頭科には当時平野実先生がおられ、臨床レベルも研究レベルも世界の最先端だったことに大変魅力を感じ、この道のスペシャリストになることを決めました。臨床に還元できる研究、患者さんの役に立つ研究をしたいという思いがあります。
久留米大の耳鼻咽喉科・頭頸部外科のテーマを教えてください
耳鼻咽頭科・頭頸部外科というのは、「脳から下、肺から上」ととても広い範囲を扱っています。五感のうち聴覚(耳)、嗅覚(鼻)、味覚を担当し、さらにはコミュニケーションに必要な音声言語に加えて、平衡機能、嚥下、睡眠時無呼吸障害や、頭頸部(頭蓋内と眼球を除く)の腫瘍性病変などがあります。それぞれの分野にいろいろな疾患があります。
久留米大耳鼻咽頭科・頭頸部外科は高い有床率を維持しており症例数もとても多いんです。基礎研究(非臨床)はもちろん大切ですが、臨床のなかで出た問題を解決するための研究も進んでいます。臨床医だからこそ出せる疑問もありますので、直接の治療に活かせる研究を多く行っています。
このように私たちの教室では喉頭に関する研究と、頭頸部癌に関する研究に力を入れており、同じ領域のテーマを歴代で60年以上一貫して行っているということは大きな強みです。
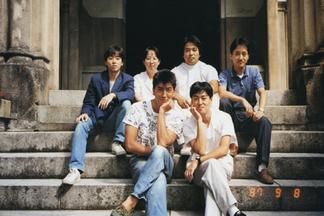

お仕事で大切にされていることはありますか?
治療で大切にしていることは、機能改善、機能温存です。たとえば頭頸部がんの場合、大きく拡大切除してそこを再建したりするのですが、そうするとやはり機能は落ちてしまいます。うまくしゃべれなくなるとか、ご飯が食べにくくなるとか、話すことができなくなったりとか。手術してがんが無くなれば長期生存が得られますが、それに伴ってQOL(生活の質)が下がってしまうのはつらいことです。なるべく機能を温存できる方法だったり、逆に出しにくかった声がうまく出せるようになったとか、鼻が通るようになって嗅覚が戻ってくるとか、食事が取れるようになったとかの機能を改善させるということも大切にしたいと考えています。それは患者さんが一番喜ばれることでもあります。
また近年では映像機器や手術器具の発展により、小さな傷で患者さんへの負担が少ない内視鏡を用いた手術があらゆる外科手術に広がっています。私の若かった頃と比べると本当に大きな進歩です。特に我々の領域で考えると、鼻は眼や脳に近いですし、耳は複雑、喉は呼吸、発声、嚥下などの重要な役割を有しています。内視鏡手術を行うことで、小さな神経や血管を避けて損傷を防いだり、病変の切除も容易になり、合併症も減ります。出血量や手術時間が短いという体への負担が少ないだけでなく、とてもメリットが大きいのです。一方で、手術を行う先生やサポート陣には高い技術と経験、そしてチームワークが必要となりますので、日々のチームのコミュニケーションを大切にしています。
どんな時にやりがいを感じますか?
大学病院ですので、治療や手術は、形成外科、外科、脳外科、放射線科など他科と協力して行うことも多いのですが、久留米大はかなり早くからチーム医療に取り組んでおり、講座の垣根を越えての交流も盛んで、他大学にはないチームワークが素晴らしいと思います。他科の先生方と協力して、一つの手術をすることも多いので、それぞれのスペシャリストの知識、技術、経験に接することで得られるものもありますし、皆さんの協力が得られるのは久留米大学の財産です。でも、ひとつでも部署のレベルが下がれば、治療全体の成績が下がってしまいますので、素晴らしい他科のスペシャリストと協働することはお互いの切磋琢磨に繋がっていると思います。
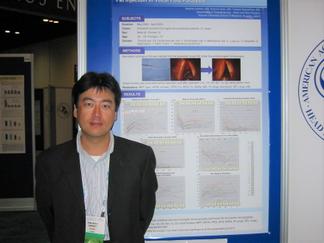

研究が進まない時にはどうやって乗り越えますか?
それは同じ組織内で話して意見を尋ねたり、自分の組織外の先生に研究会や学会で話を聞くことも大切です。思い悩んでいるのは自分だけではないということもわかりますし、また領域外の人だと全く違う意見が聞けたり、医療関係者だけではなく、いろんな職種の方との交流も大切だと感じています。今は臨床現場だけでなく、日本の若手を育てる使命もありますので、そういった意味においてもいろいろな意見やアイデアを取り入れて、皆で切磋琢磨して協力していけるよう取り組んでいます。
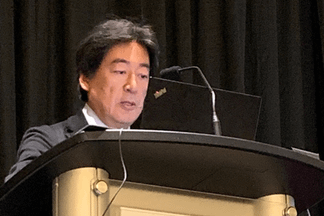
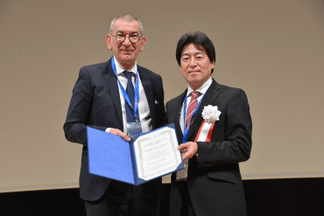
研究を離れた休日などにされていることはありますか?
テニスは最近はなかなかできませんが、ゴルフには時々出かけます。90を越えた父もゴルフが趣味で一緒にコースを回ることもあります。晴れた日に外で体を使うことが一番リフレッシュになりますね。
コロナ禍以前は、学会に行っては、皆で美味しいものを食べに行くのが楽しい時間でした。
若い方へ向けてメッセージをお願いします
自分の中で沸いた疑問はそのままにしないで、例えば文系の学生さんであれば社会制度や法律など「なんでだろう?」と感じたら自分で調べて解決する方法を模索することが大切と思います。臨床医学の世界でも想定どおりにいかないことがあります。疑問に思ったらそのままにしないのが一番大切かもしれません。自分で突き詰めて「どうしたらいいんだろう」と思って取り組んでいくと、先が開けることもあります。調べてみたら、もうすでに誰かがやってることが多いかもしれませんが、それでも自分で調べたことは残ります。
なぜだろうと思うことをぜひ大切にしてください。


久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。
久留米大学はとても恵まれた環境にあると思っています。久留米は適度に田舎で、都会で、バランスが非常にいい。自然災害も比較的少なくて、気候も温暖で食べ物も美味しい。教育レベルも高く医療が充実してますが、それだけではありません。不必要な競争が少なく、協力的な方が多いです。困ったら皆で手を差し伸べて助けるということが、ごく当たり前にあって、高いホスピタリティーの精神があります。
久留米大学は理想的な教育機関であり、医療機関、研究機関だと思います。これは世界に自慢できることです。これからも久留米大学らしく地域社会、そして世界に貢献できるよう努力していきたいと思っています。
略歴
1988年 久留米大学医学部卒業
1998年 久留米大学医学部耳鼻咽頭科学講座 講師
2003年 米国Yale大学耳鼻咽頭科 留学
2004年 久留米大学医学部耳鼻咽頭科学講座 助教授
2014年 久留米大学医学部耳鼻咽頭科・頭頸部外科学講座 主任教授