研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部外科学講座小児外科部門 加治 建教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。
医学部外科学講座小児外科部門 加治 建教授
所属部署について教えてください。
2021年11月に医学部外科学講座小児外科部門の主任教授を拝命し、鹿児島大学から久留米大学にきました。
本教室の歴史は古く、昭和38年に久留米大学外科から小児グループが立ち上げられ、昭和52年には診療科として独立しました。50年以上の歴史を有しており、臨床、研究の両面において日本の小児外科医療の先駆けとなった教室です。初代教授の矢野博道先生は小児消化管運動機能の分野を中心に多数の業績を残され、第2代の溝手博義先生は小児の栄養・外科代謝の分野、第3代の八木実先生は、消化管機能、漢方療法でと、歴代の先生方が多くの業績を残されています。
私はまだ赴任して日が浅いのですが、この久留米大学で、皆さんと新しい歴史を積み上げる一助となることを楽しみにしています。
小児外科の道を選ばれたきっかけを教えてください
私の育った環境には医療関係者がほとんどいなかったので、お医者さんというと風邪をひいたときに病院に行って注射をしてもらうようなイメージくらいで、自分も内科のドクターになるのだろうと大学に入りました。大学時代はラグビーをやっていたのですが、ラグビーの先輩方は外科の講座の先生が多かったことや、また臨床の現場で内科の先生、外科の先生を見ていくうちに、外科の手術は体を動かすという部分もあって、自分の性に合っていたのでしょうか、自然と外科の道に進みました。
成人外科か小児外科、どちらにしようかというのは、当時クリニカルクラークシップ(診療参加型臨床実習)で患者さんを見ているときに、手術した子どもたちが成長していく姿を見られるという小児外科の特徴に惹かれて、単純な理由なんですけどね、小児外科に決めました。

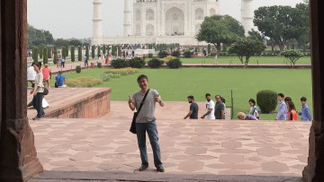
お仕事で大切にされていることはありますか?
小児外科は15歳以下の小児を主な対象として外科治療を行います。お子さんのことで、当然ご家族もとても心配されますので、ご家族のお話を聞いて、そしてしっかりと説明しながら治療を進めていくのは大切です。また、お子さんにも理解してもらって治療をすることも特に最近は必要とされています。手術してそれで全部おしまいということはなく、小児の場合は機能に関する疾患が多いので、手術後もずっと生活や食事の内容などもフォローしていくことになるのですが、小さいうちはご家族がケアできても、成人になれば本人でケアしていくことになります。小さいうちから病気のことや日常生活で気を付けることなど、自分で理解していることが、自立や自分らしい生き方ということにもつながっていくと思います。幼児、小学生、思春期と子どもの段階に合わせて、なるべく同じ目線で彼らの気持ちを聞いて、こちらも話をしていくことを大切にしています。
近年では、出生前診断を受けた胎児に対する外科的治療方針の検討にはじまり、新生児から思春期までの症例に加えて、術後の成人に至る幅広い年齢層への外科治療までを担うようになっており、小児外科は「究極のgeneralist」ではないかと考えています。そのために幅広い知識と技術を習得すべく、常に学ぶ姿勢を大切にしています。
どんな時にやりがいを感じますか?
やはり、赤ちゃんや小さかった患者さんたちが無事に成長されているのを見るときは大変喜びがあります。結婚しましたとか、子どもが生まれましたという写真を送ってきてもらったりすると、この子はこういうことで苦労したなとか、ああいうことがあったな、と懐かしく思い出すとともに、成長して自分の生活をもっている姿や、次の世代につなっがていく姿に、小児外科をやっていてよかったなと思います。
小児外科は15歳以下の小児が主な対象とはなりますが、15歳を過ぎてもそのままフォローアップしていくこともあります。小児期医療と成人期医療を繋ぐ架け橋となる移行期医療(トランジション)ということはもちろん行われていますが、特有の疾患も多いので病気自体の理解が薄かったり、慣れた先生で引き続き安心して治療を受けたいという患者さんの要望もありますので、15歳を過ぎてもフォローしていくことも多々あります。自分の世代がリタイアしても治療を引き継げるように、常にチーム全体で患者さんの病気や状況を理解するように努めています。
ご専門や興味のある研究テーマについて教えてください。
短腸症候群が一番の私の研究テーマです。2005年にカルガリー大学に留学して、短腸症候群の研究に携わったことがベースになっています。鹿児島大の教室でも継続していましたので、また久留米大でも続けられるように今少しずつ準備しているところです。


研究が進まない時にはどうやって乗り越えますか?
これをすればうまくいくというようなことは特にないんですけど、行き詰った時には一旦頭を休めて、でもやっぱり最終的には考え抜いて次の手が見えてくることもありますし、うまくいかないことも受け入れながら、また考えて。最後にはそこに向き合わないといけないと思ってやっています。
研究を離れた休日などにされていることはありますか?
グルメというわけではありませんが、外に出歩いて外食するのが好きです。今はコロナもあってなかなか外食から遠のいてしまっているのですが、段階的に出てくるフレンチなんかが好きで、妻と行くことが多かったです。久留米でもいろいろお店に行ってみたいと思っています。映画館で映画を観ることも好きです。
あとは先日はじめて屋久島に息子と行きました。鹿児島に長くいたのに屋久島には行ったことがなくて、縄文杉を見ることができて大変感動しました。

若い方へ向けてメッセージをお願いします
若い人たちには、自分の意見やアイデアを口に出すことを積極的にやってもらいたいなと思います。間違っているかもしれないと思っても、まず自分で意見を言うことは大切なことで、なにもそこに間違いはなくて、柔軟な考え方や発想というのがすごくヒントになることもあります。
また医学に限らず、広くいろいろな世界に興味を持って知識を得てもらいたいとも思います。医学という感覚を離れて、まったく別の知識であったり、違う角度で見ることで解決される問題もありますし、逆に医療の知識が全く別のところで使われたり、分野を超えた柔軟な考えでブレイクスルーがたくさん起こればいいなと思っています。
久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。
近年、少子化の進行が問題になっていますが、だからこそ、日本の未来を担う子どもたちが安心して生まれ、成長できる医療を構築することが必要であると考えています。
久留米大学外科学講座小児外科では、患者家族との対話を大切にして、安心・安全な医療を提供する事に加えて、小児外科領域の研究の発展と“心・技・体・知”を備えた心豊かな若手医師の育成を目指していきますので、何卒よろしくお願いします。
略歴
1987年 熊本大学医学部卒業
1987年 鹿児島大学医学部付属病院 小児外科医局入局
1989年 静岡県立こども病院 外科研修
1990年 鹿児島大学医学部付属病院 小児外科 医員
1999年 鹿児島大学医学部 小児外科 助手
2003年 医学博士 学位取得(鹿児島大学)
2004年 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児病態制御学分野講師
2005年 カルガリー大学GIグループ(Sigalet教室)留学
2006年 鹿児島大学病院 小児診療センター小児外科部門 講師
2012年 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 小児外科学分野 准教授
2017年 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター 特例教授
2021年 久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門 主任教授