研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】分子生命科学研究所(細胞工学部門) 齋藤 成昭 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。
分子生命科学研究所(細胞工学部門) 齋藤 成昭 教授
所属部署について教えてください。
分子生命科学研究所の細胞工学研究部門に所属しています。
分子生命科学研究所は3つの部門から構成されているのですが、それぞれの部門で、いろいろな角度から「生命活動の基本原理」にせまるような研究がおこなわれています。近年ノーベル賞を受賞された大隅良典先生や本庶佑先生の例を出すまでもなく、医学を含めたいわゆる応用科学が発展するためには、その土台となる基礎科学の発展が不可欠です。分子生命科学研究所は、平成元年に設立されて、今年(2018年)でちょうど30年になります。30年も前に「医学発展における分子生命科学の重要性」に着目して当研究所を設立された先達の先見性には頭の下がる思いです。

どのような研究を行っているのですか?
私たちの所属する細胞工学研究部門では、「細胞分裂周期制御」という現象に注目した研究を行っています。
生物の体は無数の細胞から成り立っています。例えば人間の体には約40~60兆の細胞が存在します。驚くべきことに、それらの細胞は元々一つでした。一つの細胞が成長と分裂を周期的に繰り返して2倍、4倍、8倍、、と増殖し、最終的に一つのからだが形作られます。細胞は無秩序に分裂を繰り返しているわけではありません。それぞれの細胞が置かれている状況や環境に応じて、分裂のスピードやタイミングは精妙にコントロールされています。そのコントロールの仕組みが、私たちの研究対象である「細胞分裂周期制御」です。現在は、栄養状況に応じた細胞増殖コントロールの仕組みについて、特に重点を置いて研究しています。
「細胞分裂周期制御」の研究には長い歴史があるのですが、その過程で明らかにされた重要な発見のひとつは、「単細胞生物である酵母から高等な多細胞生物である人間にいたるまで、基本的にその仕組みは同じ」ということです。ですので、私たちの研究室では、酵母細胞とヒト細胞の両方を使って研究を行っています。それぞれの特性を生かした実験や解析が可能となりますので、研究の幅を広げることができるようになります。
現代の日本において、「がん」は私たちの生命を脅かすもっとも大きな脅威であると言っても良いと思います。「細胞分裂周期制御」という観点から見てみますと、「がん細胞」とは「状況や環境に応じて分裂をコントロールする仕組みが壊れていて、無秩序に増殖を繰り返している細胞」であると言えます。そのような細胞は正常な細胞や組織を侵食し、最終的に私たちの命を奪います。私たちの研究が将来、がんの診断や治療法の発展へと結びつくことを期待しています。
研究者になったきっかけから、これまでの研究の歩みを教えてください。
「研究者になりたい」と、漠然と感じ始めたのは中学生か高校生の頃だったと思います。理科の授業で「遺伝子」の話を聞き、強い衝撃を受けました。「子は親に似る」という、一見あたり前のようで実は不思議な現象が、「遺伝子」という言葉で明快に説明できることに感動を覚えました。「当たり前のように思われているが実はよく分っていない」という現象が世界にはたくさんあって、それを理解するのが自分の使命だと感じました。天啓を受けたような気になっていたのですが、今から考えれば、単なる思春期特有の思い上がりだったみたいです。計算機科学の分野に進むか、それとも生命科学の分野に進むか、少し悩んだのですが、当時、利根川進先生がノーベル賞を受賞されたことや、「バイオテクノロジー」という言葉が流行っていたこともあり、生命科学の道を選びました。一直線に研究者を志して京都大学の理学部へと進み、そのまま大学院へと進学しました。卒業後、米国カリフォルニア州ラホヤにあるスクリプス研究所に約3年間留学し、そのあと縁あって、現所属部署の助手として着任しました。
思春期の思い上がりのまま一直線に生命科学者となったことに後悔はありません。ただ、もしあのとき計算機科学の道に進んでいれば、コンピューター会社を立ち上げて今頃は大金持ちになっていたかも、と思うことはあります(冗談です)。
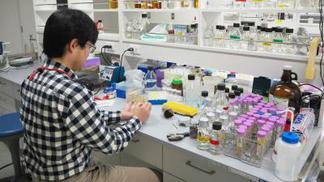

これまでの研究活動のなかで、特に大きな転機はありましたか?
転機というのとは違うかもしれませんが、研究者としての自分が形成されていく過程において、大学院時代の恩師、柳田充弘先生との出会いは大きな比重を占めていると思います。とても厳しい先生で、ほとんど毎日のように叱られました(本人いわく、齋藤を叱ったことはない、とおっしゃっていましたが、、、。今でもお会いすると、身の引き締まる思いがします)。そのおかげで、自分自身を厳しく律することができるようになりましたし、自身の研究結果を客観的に評価できるようになりました。
研究を行う上で、「自分を厳しく律すること」と、「客観的であること」はとても大切です。残念な話ですが、昔も今も、誘惑に負けて研究不正を行う人間は存在します。また、意図的では無いにしても、自身の研究結果に甘い評価を与えてしまい、結果的に「大きな過ちを犯す」者もいます。そのような、研究における闇の側面(ダークサイド)に落ちないようにするためには、自身の心の中に、しっかりとした倫理規範を持つしかありません。私の場合、そのような倫理規範の基本的な部分は、柳田先生からの教えをうけている間に徐々に形成されていったと思います。今では自分が教える側になりましたが、少しでも良い手本となれるようにと努力しています。
研究が進まない時期、どうやって乗り越えましたか?
研究が望み通り進まないのは日常的なことで、思い通りに進むことの方が稀です。思い通りに研究が進まなくても、それが普通だと思っていれば、それほど苦しくはありません。思い通りに進んでいても、進んでいなくても、くじけず、焦らず、平常心を保ちつつ研究を継続するように心がけています。「いろいろな方法や可能性を検証し続ければ、いつかは『正解』にたどりつける」という信念を持つことが大切だと思っています。
自身の経験を振り返ってみますと、失敗を積み重ねることは決して無駄ではないと思います。思い通りの結果が得られなかったということは、「試した方法や可能性が『正解』ではなかった」という事実が一つ明らかになったということです。そういう事実を消去法的に積み重ねていくことで、次第に『正解』が明らかになってきます。
研究以外に大事にしているものはありますか?
一人の時間を持つことが大切だと思っています。ただじっと座っているだけのこともありますし、何かをしながらのこともありますが、取り留めもなくただぼんやりといろいろなことに思いを巡らせていると、心が落ち着きます。そうしていると、まったくの突然に、良い研究アイディアが浮かぶこともあります。残念ながら、そのまま居眠りしてしまうか、ろくでもないことを思いつくことの方が多いのですが。
研究から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?
機械いじりが好きで、はんだごてを握って工作をしてみたり、パソコンでプログラミングをしてみたりしています(計算機科学の道に進まなかったことに対する未練かもしれません)。最近、組み立て家具を作ることも好きになりました。
あと3年ほど前から、週に1-2度のジョギングを始めました。当初は減量のために始めたのですが、思いのほか良い気分転換になります。調子の良い時には1-2時間くらいゆっくりと走り続けています。


研究をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?
私たちの行っている基礎研究は、応用研究とは異なり、人や社会に対してすぐに利益をもたらすことはありません。しかしながら、基礎研究と応用研究は車の両輪のようなもので、科学が前進するためにはその両方が同じように進むことが不可欠です。応用研究を発展させるためには基礎研究の発展が必要ですし、その逆に、応用研究の成果を利用することで基礎研究の理解が進むこともあります。
先にも述べましたが、私たちが研究している「細胞増殖周期制御」は、がん研究を発展させるための礎となるものです。また、最近注目している「栄養状況と細胞増殖」は、いわゆるメタボリックシンドロームの理解や治療につながり得る研究テーマだと思っています。遠い未来になるかもしれませんが、私たちの研究が医学や医療の発展にすこしでも役立つことになれば望外の喜びです。
研究者を目指す方へメッセージをお願いします。
どんなことにも幅広く好奇心を持つことが大切です。当たり前だと言われていることを当たり前だと思わずに、「なぜそうなのだろう?」「どんな仕組みになっているのだろう?」となんでも興味をもって調べてみてください。そしてもし、どんな書物にも納得できる答えが書かれていないような疑問にぶつかれば、それがあなたの研究テーマとなります。
久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指すことについて。
次世代の人材を育成するためには、単に知恵や知識を伝えるだけでは不充分だと思います。それらを活用して新しい知恵や知識を「創造する」方法を学生に伝えることが、「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」としての久留米大学の役割なのではないでしょうか。突き詰めれば、研究活動とは「新しい知恵や知識を創造すること」そのものです。そして、そうするための方法の本質は、「自分の頭で考える」ということです。久留米大学で学ぶ皆さんには、「自分の頭で考える」ことを身に付けていただきたいと思いますし、そのように促すことが、研究教育にたずさわる私たちの使命だと考えています。
略歴
1994年 京都大学理学部卒業
1999年 京都大学大学院理学研究科博士課程修了 博士(理学)
1999-2002年 米国スクリプス研究所 リサーチアソシエート
2002年 久留米大学分子生命科学研究所 細胞工学研究部門 助手
2005年 久留米大学分子生命科学研究所 細胞工学研究部門 講師
2009年 久留米大学分子生命科学研究所 細胞工学研究部門 准教授
2014年 久留米大学分子生命科学研究所 細胞工学研究部門 教授 現在に至る