研究・産学官連携の研究TOPICS 筋肉量と腎障害の関連性を統計学的に解明-PLOS ONEに掲載
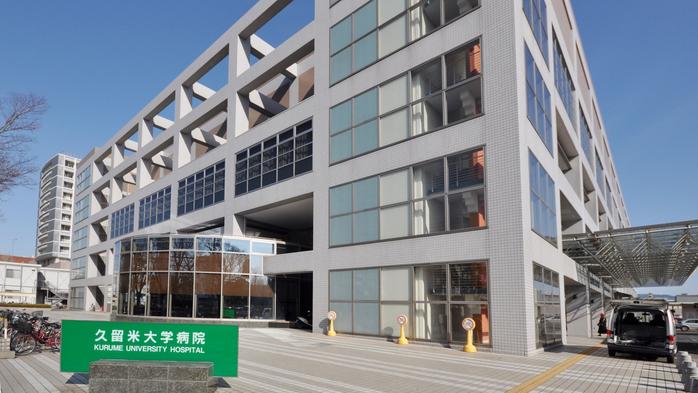
このたび、久留米大学病院薬剤部の薬剤師・樋口恭子さんが行ったがん患者の化学療法副作用に関する研究成果が、国際的学術誌「PLOS ONE」に掲載されました。
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215757
「筋肉量が少ないがん患者は通常量の1/3のシスプラチン量で腎障害を発生する」
腎障害は、シスプラチンを主体とするがん化学療法の主要な副作用です。本研究は、久留米大学病院でがんの診断を受けた約500人の患者について、身長、体重、服用薬剤などの患者背景を調整した上で、シスプラチンと腎障害の関連性を統計学的に調べました。特にTPF療法 注)とよばれる化学療法に限った時、薬剤MgO注)の服用がなく、薬剤NSAIDs注)の服用がある筋肉量が少ない患者は、通常安全とされるシスプラチン基準量の約1/3の量で腎障害を発生すること、すなわち、がん治療の化学療法では、患者の特性や服薬状況を考慮してシスプラチン量を調整する必要があることが示唆されました。
注)
TPF療法:ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシルの薬剤を使った頭頸部癌などに用いられる化学療法。
MgO:酸化マグネシウム、腎障害の予防効果が報告されている。
NSAIDs:非ステロイド性抗炎症薬、腎障害を起こす可能性があることが指摘されている。
樋口さんは、薬剤師と本学大学院生という二足のわらじを履きながら、抗がん剤の一種であるシスプラチンと腎障害の関連性を統計学的に調査しました。
筋肉量の少ない患者には、少ない量のシスプラチンで腎障害を発生することが示唆され、今後TPF療法を行う際のシスプラチン使用量に関する新たな指針の一つとなり得る研究成果です。
【関連サイト】
久留米大学大学院医学研究科 https://www.kurume-u.ac.jp/faculty/gmed/
久留米大学バイオ統計センター http://www.biostat-kurume-u.jp/